ハッピーミルクフェスタin福岡2025×土日ミルク
九州の酪農と牛乳の魅力を体験できるイベント『ハッピーミルクフェスタin福岡2025』。さまざまな体験型コンテンツが用意され、多くの来場者でにぎわったこのイベントでは、『土日ミルク』を参考にしたコンテンツが数多く活用されました。
イベント開催に込められた想い、『土日ミルク』コンテンツに対する見解、そしてこれからの展望などについて、主催者の皆さまにお話を伺いました。
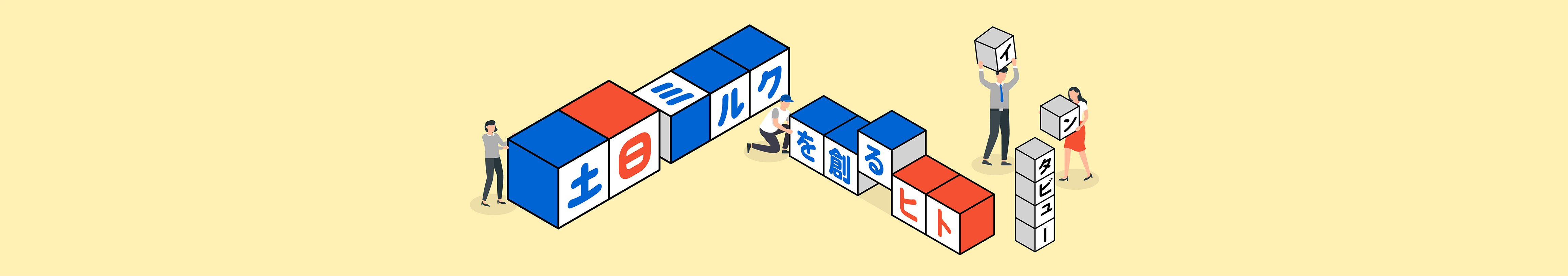

熊本のとある地域での取り組みとして始まり、全国展開して30年近い歴史を持つ全国酪青女による「父の日に牛乳(ちち)を贈ろうキャンペーン」と、「土日ミルク」が連携。多様な活動を支える事務局の支援体制や、今後のコラボへの期待などをお聞きしました。
【今回の土日ミルクを創るヒト】
全国酪農青年女性会議
中村 俊介(なかむら しゅんすけ)さん/委員長
全国酪農業協同組合連合会
隈部 洋(くまべ ひろし)さん/代表理事会長
炬口 浩司(たけのくち こうじ)さん/総務部 副部長
板倉 雅治(いたくら まさじ)さん/総務部
上原 直子(うえはら なおこ)さん/総務部
【記事のポイント】
・地域のニーズや思いに根ざした多様な取り組み
・ツール提供、成果共有で草の根的な活動もサポート
・消費拡大、理解醸成活動は“規模より回数”がカギ
・“活性化”と“発信力アップ”につながるコラボへ
【活用した土日ミルクコンテンツ】
・土日ミルク イベント活用ツール
全国酪農青年女性会議(酪青女)では、毎年6月の父の日に合わせて、「父の日に牛乳(ちち)を贈ろう!キャンペーン」と題した、牛乳の消費拡大や酪農への理解促進を目的とする活動を全国各地で実施しています。

毎年5月中旬から7月にかけて、その傘下の各地の酪農組合の青年部・女性部を中心として、全国各地で140~150件ほどの活動が展開されます。農政局や県庁・市庁での牛乳贈呈式や、駅前や道の駅でのPRイベント、地元の幼稚園・保育園の訪問など、内容は地域によりさまざまです。全国に6ブロックある酪青女の地域会議、県の支部会議、各地の酪農業団体など、運営主体も多岐にわたっており、地域に根差した自発的な活動が特徴です。

活動の広がりを支えているのが、全国酪農業協同組合連合会(全酪連)や全国の酪農組合の事務局メンバーの皆さんです。「活動に必要なツール類(ロゴの入ったのぼり、ノベルティグッズなど)の制作・提供から成果の取りまとめと発信まで、現場に直接関わるのではなく、あくまで地域の自主的な活動を尊重しながら裏方としてお手伝いするのが私たちの役割です」(板倉さん)
配布されるツール類には、「ミルメーク」や、保護者の似顔絵を描くための専用画用紙などがあり、いずれも複数地域からの要望に基づき、事務局が一括発注・分配しています。「ミルメーク」は、キャンペーンのロゴと「大切な人へのメッセージ」書き込み欄を印刷したオリジナルパッケージを2万パック用意するとのこと。地域単位の小ロットでは制作が難しいこうしたグッズも、全国規模の連携により活用可能となります。
各地での活動成果は、酪青女の地域会議などを通じて事務局が集約。「例年7月開催の酪青女全国発表大会でも報告されます。他地域の好事例が共有されることで、各地の活動の質をさらに充実させることができます」(上原さん)
こうした地域密着型のキャンペーンと、「土日ミルク」のコラボが今年度からスタート。行政への訪問や各種イベントなどで、のぼりやチラシといった土日ミルクツールが活用されました。
炬口さんは今回のコラボについて、「私たち酪農乳業団体が有機的につながり、お互いの活動を補完できる関係をつくることが大切」と語ります。「父乳キャンペーン」は、地域のニーズや思いに寄り添って草の根的な取り組みもしっかりフォローする、土日ミルクはメディア活用も含めて幅広くPRするなど、「お互いの持ち味や得意分野を活かすことで、相乗効果によって活動を活性化させていきたい」と話します。
この“活性化”とは、単に複数の活動を集約して規模を拡大することではなく、活動の回数を維持しながら内容の充実を図ること。消費拡大や理解醸成など、社会への継続的な情報発信が必要なテーマでは「活動の規模よりも回数が大切」と強調する板倉さんは、「県単位で細かく見ると、イベントやグッズ配布などは年間を通じて数多く行われています。「土日ミルク」と連携し、回数をこなすことで多くの目にふれる機会をつくること。こうした活動が酪農家さんに力を与えるものになれば」と今後の展開に期待を寄せています。

熊本県では6月から7月にかけて、「父の日に牛乳(ちち)を贈ろう!キャンペーン」に関連して10回以上の活動が行われました。7月6日に阿蘇ミルク牧場で開かれた「酪農を楽しく学ぼうツアー」にも多くの家族連れが参加し、酪農クイズやバターづくり体験、乳しぼり体験などを楽しんでいました。






「こうした現場で、消費者から『毎日飲んでいます』『おいしいですね』と声をかけてもらうことは、酪農家にとっても仕事の大きな励みになるものです」と話すのは、酪青女の中村俊介委員長です。この日は、自ら子どもたちの手を取って乳しぼりのサポートにあたるなど、酪農家仲間と共にイベント運営にも携わっていました。

熊本県の生乳生産量は九州最大、全国3位の規模を誇る一方、酪農家の減少は顕著で、他県と同様に後継者育成と持続可能な経営の確立が大きな課題となっています。「持続可能な酪農経営のためには、女性や若手層の活躍が不可欠。かれらの力を高めるため、酪青女としても農家同士のつながりの場づくりを重視しています」と中村さんは話します。
一方で消費拡大・理解醸成活動については、牧場見学や乳牛とのふれあいが防疫対策の面で難しくなっていることから、「情報発信のあり方も含めて、活動内容を見直す時期にきているのでは」と指摘。「業界全体が連携を深めながら、SNSやメディアも積極的に活用して、より幅広く効率的に酪農の価値を発信していく必要があります。今回のコラボがそのきっかけになるといいですね」と期待を込めます。

1997年、熊本県大津町の酪農女性部が、父の日に合わせて町長や行政の方々へ牛乳を贈る活動を始めたのが、「父の日に牛乳(ちち)を贈ろう!キャンペーン」の原点です。ちょうど私が県や九州の酪農・生乳販売団体に携わっていた時期だったので、大津町の取り組みを「行政を巻き込んだ消費拡大活動の好事例」として会議などで取り上げ、各地に紹介し他地域へと広めていきました。
2004年に酪青女の全国委員長を拝命した際、地域会議単位ではなく、全国のみんなで同じ目標を掲げ、心を一つにして取り組める消費拡大活動が必要と考え、このキャンペーンを提案しました。その2年後から全国展開がスタートし、各地の酪農家仲間 “酪友”たちが、思いを共有し連帯する活動の一つとして現在まで続いています。
熊本県酪農業協同組合連合会は「らくのうマザーズ」として牛乳・乳製品の製造・販売も手掛けているので、「販売なくして生産なし」という意識が酪農家たちに根付いています。その熊本から始まったキャンペーンが全国に広がることで、販売への理解が他地域の酪農家にも浸透してきたのは、大きな成果といえるでしょう。
日本にとって食料自給率の向上は喫緊の課題です。酪農は直接的な食料生産にとどまらず、国土・農地の保全や、食と命の大切さを伝える教育的役割も担い、食料自給に貢献しています。こうした多面的価値を社会に発信しながら、酪農家自身も経営改善を重ね、楽しい酪農を実現していくことが、次世代の担い手が育つ環境づくりにもつながると考えています。